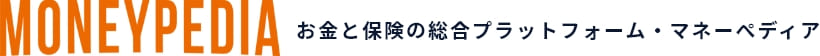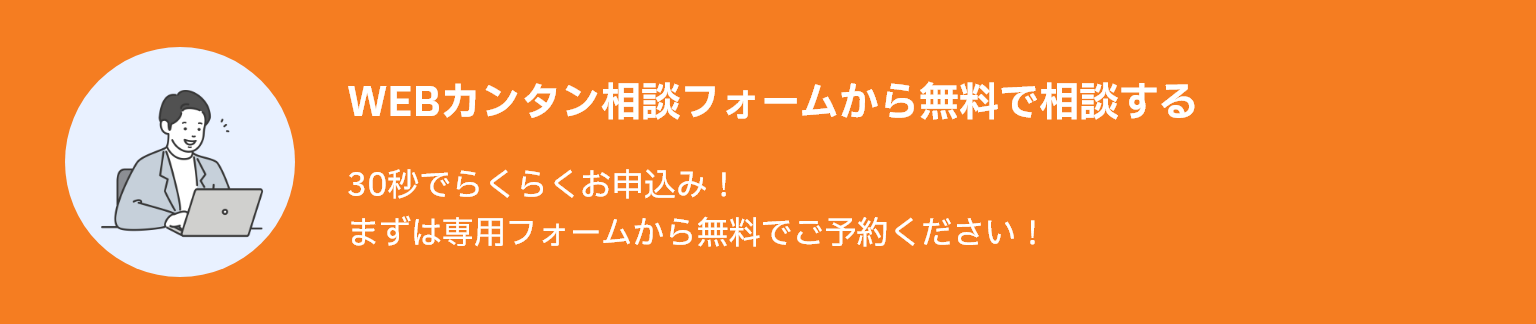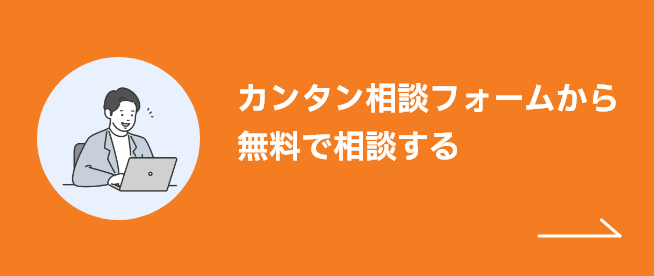【FP監修】学資保険の返戻率はカラクリに注意!貯蓄性を高める方法や選び方も紹介

子供の教育費に備える学資保険で、注意が必要なのが返戻率です。
返戻率を高めれば、お得に学資保険を利用できるのです。
本記事では、学資保険の返戻率の基礎知識や仕組みを解説します。
また、返戻率に惑わされない考え方や返戻率を上げるコツ、返戻率の高い学資保険を紹介します。
記事監修者
SYN Group 株式会社
笈田 恩来
学資保険の返戻率とは
そもそも学資保険とは、子供の教育費に備えるための貯蓄型の保険です。
毎月、決まった保険料を支払うことで、子供の進学や大学入学などに合わせて、満期保険金や祝金を受け取れます。
学資保険には、契約者が病気や障害で保険料を払えなくなったときの保険料免除や、家族が病気やケガをしたときの医療保障などの特約もあります。
そのような学資保険には、返戻率があります。
学資保険の返戻率とは、支払った保険料に対して、受け取った満期保険金や祝金がいくらなのかを表す割合のことです。
返戻率が100%を超えれば、支払った保険料よりも、多くの満期保険金や祝金を受け取ったことになります。
逆に返戻率が100%未満なら、受け取った満期保険金や祝金よりも、支払った保険料の方が多いことになります。
ただし、むやみに返戻率の高い学資保険を選べば良いというわけでもありません。
ここでは学資保険を選ぶ前の前提知識として、学資保険の返戻率の計算方法や一般的な返戻率などの基礎知識を解説します。
学資保険の返戻率の計算式
学資保険の返戻率は、次のような計算式で求められます。
返戻率=受け取った総額保険金÷支払った総額保険料×100
総額保険金は学資金や祝金、満期保険金、学資年金など保険会社から受け取った全ての保険金です。
総額保険料は年払いや月払いなどに関係なく、学資保険のために支払った保険料の全てになります。
返戻率が高ければ高いほど、貯蓄性の高い学資保険と言えるでしょう。
貯蓄性の高い学資保険に加入したいなら、返戻率の高い学資保険が望ましく、返戻率が低い学資保険は好ましくありません。
しかし、返戻率が低い学資保険には手厚い保障がついているなどメリットもあるのです。
学資保険の返戻率にも、一長一短があるので、自分に合った学資保険を探すのが良いでしょう。
学資保険の一般的な返戻率
日本郵政グループのかんぽ生命や、大手生命保険会社である明治安田生命、ソニー生命などの学資保険の返戻率を、各社のWebサイトのシミュレーションを使って調べてみました。
すると、一般的な日本円建ての学資保険の返戻率はおおよそ103〜110%になります。
多くの保険会社が、高い返戻率をアピールしているので、返戻率100%を超える結果となりました。
返戻率は、契約時に付加した特約や保険金の受け取り方、保険料の支払い方など、さまざまな条件によって変わります。
そのため、一般的な学資保険の返戻率は、目安として参考にしてください。
学資保険の返戻率と銀行預金の利率
繰り返しになりますが、一般的な学資保険の返戻率は103〜110%ほどです。
学資保険は、長期間加入することが前提の保険です。
ここでは、学資保険の返戻率を年利にした場合と、銀行預金にした場合を比べてみましょう。
例えば、返戻率103%の学資保険に10年間加入し、トータル100万円の保険料を支払ったとしましょう。
すると、返戻率からトータルで受け取った保険金は3万円になります。
3万円を10年間かけて受け取っていると考えられるので、1年で3千円の保険金を受け取ることになりますね。
つまり、年利は3千÷100万円×100=0.3%になります。
それでは、続いて銀行預金の年利を確認します。
メガバンク3行の普通預金の年利は、0.001%です。
100万円を1年間預けたら、10円の利息を受け取ることになります。
銀行の普通預金と比べると、学資保険の利率はかなり良いことがわかります。
では、定期預金ではどうでしょうか。
現在、高い利率を誇っている定期預金は商工中金のネットバンキングサービスです。
商工中金のホームページで確認すると、年利0.22%になるようです。
確かに学資保険の利率に近い数字です。
しかし学資保険の返戻率は、保険としての保障がある上に、返戻率を高める工夫もできます。
単純に利率だけを比較すると今では、銀行預金よりも学資保険の方が高くなる可能性があるでしょう。
学資保険の返戻率の推移
学資保険の返戻率の推移を確認すると、実は学資保険の返戻率は下がっています。
数年前までなら、円建てでも返戻率が110〜120%の学資保険が多数ありました。
しかし、今ではほとんど見かけなくなっています。
なぜ返戻率の推移が下がっているかというと、マイナス金利政策の影響です。
マイナス金利とは、民間金融機関の銀行である日本銀行に、民間金融機関がお金を預けるとき、預ける側が利息を支払う政策のことです。
本来、利息は預けた側が受け取るものですが、マイナス金利は、その逆のことをしています。
マイナス金利になってから、保険会社も利息を支払って日本銀行にお金を預けています。
すると、利益が減ってしまうので、保険会社としては利益を上げる努力をしなければなりません。
そこで、保険会社は保険料を上げるようになりました。
返戻率は、支払った保険料に対する受け取った保険金の割合です。
保険料が上がれば、返戻率は下がってしまいます。したがって、学資保険の返戻率は下がっているのです。

学資保険の返戻率にはカラクリがある
返戻率の基礎知識について、ご理解いただけたと思います。
返戻率は支払った保険料に対する受け取った保険金の割合です。
返戻率が高ければ、支払ったお金よりも、受け取ったお金の方が多いことを表します。
返戻率は工夫次第で高めることができます。
しかし逆に、下げてしまうこともあるのです。
また、返戻率が高ければ、必ずしも貯蓄性も高いわけではありません。
ここでは、学資保険の詳しい仕組みについて、紹介します。
学資保険の返戻率と貯蓄性の関係
学資保険の返戻率が高ければ、支払った保険料よりも受け取った保険金が多いことになりますね。
しかし、返戻率が高いからといって、必ずしも貯蓄性が良いとは限りません。
なぜなら、返戻率は保険料の払込期間や、保険金の受け取り方によって変わるからです。
例えば、返戻率110%と103%の2つの学資保険があるとします。
返戻率110%の方は加入から、10年間で保険料を支払い、18年後に保険料を分割で受け取るとしましょう
。一方の103%の方は、加入から18年間かけて保険料を支払い、満期で一括で保険金を受け取るとします。
返戻率が高い方が受け取る保険金も多いです。
そのかわり短期間で保険料を支払わなければならない上、保険金を受け取るのも先になっています。
実は例のような学資保険は、同じ会社の同じ学資保険で、違うプランとして売り出されていることがあります。
つまり返戻率によって受け取る金額は違っても、期間や負担を考慮すると貯蓄性や学資保険の価値は、返戻率の高低に関係なく変わらないのです。
返戻率が高いからといって、貯蓄性があったり、優れた学資保険であるわけではありません。
学資保険の返戻率は調整できる
学資保険の返戻率は、保険料を支払う期間や保険金を受け取るタイミングによって調整できます。
返戻率を高めるためのポイントは、保険会社に長く運用してもらうことです。
保険会社は、加入者から支払いを受けた保険料を運用します。
運用から生まれた利益を、返戻率として保険金に上乗せしたり、保険会社の他の事業のための資金にしたりします。
つまり、支払った保険料を長く運用してもらうことで、多くの資金を増やせるのです。
保険料100万円を一括で払うのか、10年かけて払うのかでは運用成果が異なります。
加入から20年後に、保険金を受け取るとしましょう。
一括で支払えば100万円を20年間運用できますね。
しかし10年間の分割払いでは、100万円を運用できるのは10年間だけです。
つまり、払込期間が短い方が高い返戻率になります。
では、加入から20年後に100万円の保険金を一括で受け取る場合と、4年に分割して受けとる場合を比較してみましょう。
一括で受け取ると、もう運用はできませんよね。
しかし分割で受け取れば、受け取っていない分は運用してもらえます。
例で言えば、さらに4年間の運用ができるのです。
すなわち、学資保険の保険金は、受け取る時期を後にするほど、高い返戻率になるのです。
以上のように、学資保険の返戻率は、保険料の支払い期間と保険金の受け取るタイミングによって変わるのです。
学資保険を返戻率のみで選ぶリスク
返戻率は保険料を早く支払い終わって、保険金の受け取るタイミングを後ろ倒しにすればするほど高くなります。
しかしその方法で高い返戻率にするのが、自分に合った学資保険の活用方法とは限らないでしょう。
返戻率だけに目を向けてしまうと、自分のニーズを満たせない恐れがあるのです。
払込期間を短くしすぎて、負担が大きくなり払えなくなっては意味がありません。
また、本当に必要な時に保険金を受け取れずに、困ってしまうかもしれません。
さらに、学資保険には特約があります。
特約をつけると保険料も高くなり、返戻率が低くなる可能性があります。
しかし、本当に必要な特約ならつけるべきですよね。
学資保険を選ぶポイントは、返戻率以外にもたくさんあります。
返戻率だけではなく、総合的に自分に合っているかどうかが、学資保険を選ぶ時に気をつけることです。

学資保険の返戻率に惑わされない選び方
返戻率だけでは、本当に自分に合った学資保険かどうかはわかりません。
返戻率に惑わされないための、学資保険の選び方があります。
ここでは、学資保険を選ぶときに、考慮すべきポイントを紹介します。
学資金の用途・受け取り時期を決める
返戻率の高さよりも、自分がいつ受け取りたいかで学資保険の種類やプランを選ぶのがおすすめです。
なぜなら、学資金が必要なときに受け取れないと、学資保険の意味がないからです。
例えば、大学入学時にまとまった資金が必要なのに、その前に分割で保険金を受け取ってしまっては、大学の入学金を支払えません。
そのため、学資保険への加入を検討する際には、いつ・いくらの保険金を受け取りたいかを明確にしましょう。
受け取りたいタイミングが明確になってはじめて、返戻率の高い学資保険を探すのがおすすめです。
用途・受け取り時期に合わせてプランを選ぶ
保険金を受け取る時期を選ぶに当たって、学資保険で選べるタイミングはいくつかあります。
ここでは、その中で代表的なものを紹介します。
大学入学に合わせて一括で受け取る
大学入学時に一括で、満期保険金を受け取ることができます。
子供の進学で一番資金が必要なのが、大学の入学金でしょう。
将来的に、子供を大学に通わせたいという意思が強い方には、特におすすめの受け取り時期です。
小・中・高・大の進学ごとに受け取る
進学するごとに、祝金を受け取るプランです。
特に私立への進学には、まとまった資金が必要になるでしょう。
私立への進学を視野に入れている方に、向いています。
ただし、学資保険に加入してから、あまり時間が経たない内に保険金を受け取ることになるので、返戻率は高くありません。
一方で、もし祝金の受け取りが不要なら、そのまま保険会社に預けておくこともできます。
将来の、資金が必要なときのために据え置くのも1つの選択肢です。
大学在学中に毎年受け取る
大学在学中に資金が必要な場合に、毎年保険金を受け取るプランです。
大学入学時に、一部の資金を受け取ったあと、毎年の授業料などのために、年金のように毎年受け取る仕組みです。
分割で保険金を受け取るため、ここまで紹介してきた受け取り方の中で、最も返戻率が高い受け取り方です。
低解約返戻金型終身保険の利用も考える
学資保険だけでは不安な場合やさらに効率よく学資金に備えたい場合は、低解約返戻金型終身保険の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
低解約返戻金型終身保険は、保険料を全て払い終わったあとに、保険を解約すると支払った保険料よりも多くの解約返戻金を受け取れるという特徴のある保険です。
子供が産まれてから成長するまでの10〜15年の間に保険料の支払いを終わらせて、子供の進学などの時期に合わせて解約すれば解約返戻金が学資金の代わりになるはずです。
契約者の年齢や健康状態によって、保険料は変わります。しかし健康で若い状態であれば、学資保険のように使える保険です。
保障特化タイプの学資保険は避ける
学資保険には、教育資金の準備に特化したものと、親や子供の病気やケガなどの保障に特化したものの2種類があります。
保障特化タイプの保険は、親に万が一のことがあったときに、育英年金や死亡保険金、入院給付金などを受け取れます。
しかし、その分多めに保険料を支払う必要があり、返戻率が低くなっていしまいます。
学資保険の最大の目的は、子供の教育費に備えることです。
もちろん、保障をつけてもかまいません。
ただ、必要最低限に止めておくのがベストです。

学資保険の返戻率・貯蓄性を賢く高めるポイント
ここまでお伝えしてきたように、学資保険は自分にあったものを選ぶのがセオリーです。
いつ、いくらの保険金を受け取りたいのか、プランを練っておきましょう。
ただ、学資保険をどのように活用したいかがある程度明確になったら、返戻率を上げる工夫をしてみてください。
ここでは、賢く返戻率を高めるポイントを解説します。
学資保険の支払い期間を短く済ませる
学資保険の保険料をなるべく早く支払い終わって、支払い期間を短くすると返戻率を上げられます。
理由は、まとまった資金を保険会社に長く運用してもらえるからです。
学資保険の支払い期間には、さまざまなものがあります。
契約時の一括払いや、子供の年齢に合わせた期間などです。
子供の年齢に合わせる場合は10歳や15歳、18歳までに払い終わるパターンが多いようです。
無理のない範囲で、保険料を払い切れる最短を目指すのがいいでしょう。
学資金の受け取りを先延ばしにする
学資保険の保険金の受け取るタイミングを、先延ばしにすれば返戻率が高まります。
理由は、支払い期間を短くするのと同じで、まとまった資金を保険会社に長く運用してもらえるからです。
そのため、子供の進学に合わせて祝金を受け取るより大学の入学時に受け取る方が、多くの保険金を受け取れます。
また、大学入学時に受け取るよりも大学在学中に、毎年に分けて受け取る方が保険金は多くなります。
より資金が必要な私立に入学させないなら、祝金はできるだけ受け取らず、先延ばしにするのが良いでしょう。

返戻率の高い学資保険おすすめ5選
ここまで返戻率の基礎知識やその仕組み、返戻率に惑わされない学資保険の選び方、返戻率を高める工夫などについてお伝えしてきました。
返戻率が高いだけでは、自分に合った学資保険かはわかりません。
しかし、学資保険の活用目的が明確になったなら、返戻率の高い学資保険を選ぶのがお得ですよね。
そこで、ここでは返戻率の高い学資保険や高める工夫ができる学資保険を紹介します。学資保険を選ぶ参考にしてください。
返戻率の高い学資保険①ソニー生命学資保険
ソニー生命学資保険は、高い返戻率を誇っています。高い場合は106.3%もの返戻率を期待できますよ。
ソニー生命学資保険の魅力は、受け取りプランと保険設計を柔軟に決められることです。
保険金の受け取り方は、次の3つのタイプに分かれています。
- 中・高・大の進学に合わせて受け取る
- 大学入学時に受け取る
- 大学入学から22歳まで分割で受け取る
3つ目のタイプを選べば返戻率を、最も上げることができます。
払込期間は子供の年齢が10・15・17・18歳になるまでのどれかを選べますよ。
満期は17・18歳か、20・22歳です。柔軟な保険金の受け取りと、保険設計が魅力です。
返戻率の高い学資保険②明治安田生命のつみたて学資
返戻率が、数ある保険会社の中でトップクラスの109%まで見込めるのが、明治安田生命のつみたて学資です。
最大の特徴は、保険金の支払い総額を300万円以上にすると、高額割引が適用されることです。
割引によって保険料が安くなるのに、受け取れる保険金は変わりません。
そのため、高い返戻率を維持できるのです。
明治安田生命のつみたて学資に加入すると、保険金は大学入学時から受け取りが始まり、在学中は毎年受け取れるようになっています。
学資金が最も必要な大学生活で、充実した備えができるでしょう。
返戻率の高い学資保険③フコク生命学資保険みらいのつばさ
フコク生命学資保険みらいのつばさは、兄弟割引というユニークな制度があります。
2人目の子供から、支払う保険料が割引されます。
割引額は、満期保険金10万円ごとに月10円です。
満期保険金が300万円なら、毎月300円の割引ですね。
学資保険は、10年以上支払い続けるので、数万円以上の割引額になるでしょう。
みらいのつばさの保険金を受け取るタイミングには、ステップ型とジャンプ型の2種類があります。
ステップ型は幼稚園から大学の進学ごとと満期時に受け取れます。ジャンプ型は、大学入学時と22歳のときにまとまった額をもらえます。
保険料の支払い期間は、子供の年齢が11、14、17歳の時までの3つの選択肢があります。
返戻率の高い学資保険④かんぽ生命はじめのかんぽ
かんぽ生命のはじめのかんぽは、日本郵政グループのかんぽ生命が取り扱っているため、安心感のある商品と言えるでしょう。
保険金受け取りのタイミングは、次の3つのプランから選べます。
- 大学入学時に受け取る
- 中・高・大の進学に合わせて受け取る
- 大学入学から22歳まで分割で受け取る
返戻率を高めるには、3つ目がおすすめです。
はじめのかんぽは、充実した保障をつけられるのが特徴です。
子供の入院特約や手術特約など、万が一のときに心強い保障です。
しかし、その分保険料が高くなって、返戻率が下がってしまうので、注意が必要です。
返戻率の高い学資保険⑤日本生命ニッセイ学資保険
日本生命ニッセイ学資保険には、祝い金なし型とあり型の2種類があります。
なし型は、子供の大学入学から22歳までに毎年、保険金を受け取れます。
あり型は、小学校から大学入学までの各進学タイミングと、大学在学中の22歳までの毎年、受け取るようになっています。
高い返戻率にしたいなら、なし型がおすすめですね。
また学資保険の中ではめずらしく、配当金があります。
配当金とは、保険会社の運用成績が良いときに、余剰分を保険加入者に配るお金のことです。
学資保険は、インフレに弱いというデメリットがあります。
しかし、配当金があれば定期的に資金がもらえるので、インフレに負けないようになるでしょう。

学資保険以外の子供の教育資金に備える方法
学資保険の返戻率を中心に、学資保険について解説してきました。
しかし、子供の教育資金に備える方法は、学資保険だけではありません。
本記事をご覧になっている方の中には、学資保険と合わせて、他の方法でも備えたい方もいるでしょう。
ここからは、学資保険以外の子供の教育資金に備える方法を紹介します。
学資保険と組み合わせることで、効率的に準備できるでしょう。
銀行預金
銀行預金でも子供の教育費に備えることができます。
ただし、現在の低金利下ではあまり効率的な方法とは言えません。
本記事でも紹介したように、銀行預金の利率は、とても低くなっています。
そのため、自分が預けた金額分しか備えられず、資金を増やしながら貯蓄していくのには不向きです。
資産運用
資産運用は株式や投資信託、債券などに投資して、資金を増やしながら子供の教育資金を準備していく方法です。
上手に運用できれば、かなり効率よく資金を貯められるでしょう。
リスクを抑えながら、年利3〜5%くらいを目指してコツコツ運用してけば、学資保険よりも多くの資金を準備できる可能性があります。
ただ、資産運用についての勉強と実践が欠かせません。
また、当然損してしまうリスクもあります。
勉強時間を割ける余裕と、リスクを背負える覚悟があればとても優れた方法でしょう。
学資保険と合わせて活用することをおすすめします。
教育ローン
教育ローンは、子供の教育資金を準備するために、国や企業からローンを組んでお金を借りる制度のことです。
必要なときに、まとまった資金を貸してもらえるので、急に資金が必要になったときに役立ちます。
しかし、教育ローンは借金です。
利息をつけて、必ず返済しなければなりません。
国の教育ローンは金利が比較的安いですが、審査が厳しい傾向にあります。
借金なので、利用は慎重に検討することをおすすめします。
奨学金
奨学金には、民間の法人が運営しているものもありますが、代表的なのは日本学生機構の奨学金でしょう。
日本学生機構の奨学金には、給付型と貸与型があります。
しかし基本的には、貸与型を利用することになるでしょう。
貸与型には、利息の付かないものと利息がつくものがあります。
利息の有無は、子供の成績や家庭の所得状況によって異なります。
奨学金も借金の1つです。必ず返済しなければなりません。
教育ローンと同じように、利用は慎重に検討しましょう。
まとめ
本記事で見てきたように、学資保険の返戻率にはたくさんの注意点がありましたね。
自分だけで学資保険の検討をするのは、難しく感じるでしょう。
そこで、返戻率を意識しながら、満足のいく保険内容にするためにもプロに相談するのがおすすめです。
専門家の目線から、返戻率の詳しい仕組みやあなたに合った学資保険を一緒に考えてくれるはずです。
最後に、本記事の内容をまとめるので、情報の整理にお使いください。
- 学資保険の返戻率とは、支払った保険料に対して、受け取った満期保険金や祝金がいくらなのかを表す割合のこと。
- 返戻率の計算式は、「返戻率=受け取った総額保険金÷支払った総額保険料×100」。
- 一般的な学資保険の返戻率はおおよそ103〜110%。
- 単純に利率だけを比較すると今では、銀行預金よりも学資保険の方が利率が高くなる可能性がある。
- 学資保険の返戻率は、下がっている。
- 返戻率は保険料の払込期間や、保険金の受け取り方によって変わる。
- 返戻率に惑わされないため、保険金を受け取るタイミングを決めたり、低解約返戻金終身保険を活用したり、保障特化タイプの学資保険を避けたり工夫するのがおすすめ。
- 返戻率は、払込期間を短くしたり、保険金を受け取るタイミングを先延ばしにすると高くなる。
- おすすめの学資保険には、ソニー生命保険学資保険、明治安田生命つみたて学資、フコク生命みらいのつばさ、かんぽ生命はじめのかんぽ、日本生命ニッセイ学資保険などがある。
- 学資保険の他に、子供の教育費に備える方法として、銀行預金や資産運用、教育ローン、奨学金などがある。
「まずは気軽に保険のことを相談してみたい!」という方にお勧めなのが、Moneypediaのオンライン保険相談サービスです。
保険のことをいつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談することが出来ます。
まずは一度、下記リンクからご相談されてみてはいかがでしょうか。
Moneypediaのオンライン保険相談サービス
いつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談